
「松井 康真がゆく原子力最前線」第2回は、2025年4月に日立GEベルノバニュークリアエナジーの社長に就任した久持 康平にインタビュー。カーボンニュートラル社会とデジタル社会の両立を支える安定的なエネルギーシステムの一つとして原子力発電が再注目され、国内発電所の再稼働、小型原子炉の商用化などにより原子力事業が新たな展開を迎えている中、原子力発電の安全性向上と社会からの信頼獲得、事業の成長に向け、久持社長はどのような思いで経営の舵を取っていくのでしょうか。
前編では、久持社長が大学で原子力工学を選んだ理由、これまでの歩み、福島第一原子力発電所事故のこと、GEベルノバとの協創について聞きました。


松井:はじめまして。本日はどうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させていただくと、私は1986年にテレビ朝日に入社して25年間アナウンサーとして勤め、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故をきっかけに原子力事故専従の記者となりました。現在はフリーアナウンサー、ジャーナリストとして活動しております。久持社長は、今年4月に日立GEベルノバニュークリアエナジーの社長に就任されたとのことですが、これまでずっと原子力分野の技術者として歩んでこられたのですか。
久持:はい。1993年に日立に入社し、主に安全対策の分野に従事してきました。例えばBWR(Boiling Water Reactor:沸騰水型原子炉)のシビアアクシデント対策や、確率論的安全評価などです。確率論的安全評価とは、原子力施設に起こり得るさまざまな事象の発生確率とその影響を定量化し、リスクを算出して、安全性を評価する手法のことです。
松井:九州大学の大学院を出られたとのことですが、ご出身も九州でしょうか。
久持:はい。私は長崎県松浦市の出身で高校まで長崎で過ごしました。その後、九州大学・大学院で原子力工学を学びました。
松井:大学で原子力工学を選ばれたのは、どのような理由からですか。
久持:やはり長崎県ということもあり、子どもの頃から原爆について話を聞く機会が多く、戦争や原子力について考えることが自然と多くありました。その中で、日本が資源に乏しい国であることが戦争の根本的な原因だったのではないかと自分なりに考え、将来はエネルギー資源の問題を解決できるような仕事がしたいと思うようになりました。また、原爆を開発した技術者の話を聞いたとき、自分は「原子力を平和のために生かせる技術者になりたい」と強く思ったことも理由の一つです。
松井:原子力工学の中にもさまざまな専門分野がありますが、学生時代から原子炉の安全評価について研究されていたのですか。
久持:いえ。学生の頃はどちらかというと研究者をめざしていて、量子力学や素粒子物理学など、原子力でも理論寄りの分野に興味がありました。例えば加速器を用いて陽子と金属の衝突実験を行い、核破砕反応を解析するといった研究に取り組んでいました。このような研究の産業応用というと主に医療分野になりますが、いざ就職するという段階になったとき、広く社会全体を支えることに貢献したいと思うようになって、エネルギー関連の企業を志望しました。
松井:それで日立に入られたのですね。どうして日立だったのでしょう。
久持:エネルギー関連の仕事の中でも、モノづくりがしたい、大きな原子力施設の建設に携わりたいと思ったからですね。必然的に就職先は絞られますが、その中でもなぜ日立だったのかというと、原子力技術のあるべき方向についてよく議論をしていた先輩方から薦められたことが理由の一つです。「真面目に原子力に取り組んでいる会社」という印象も強くありました。
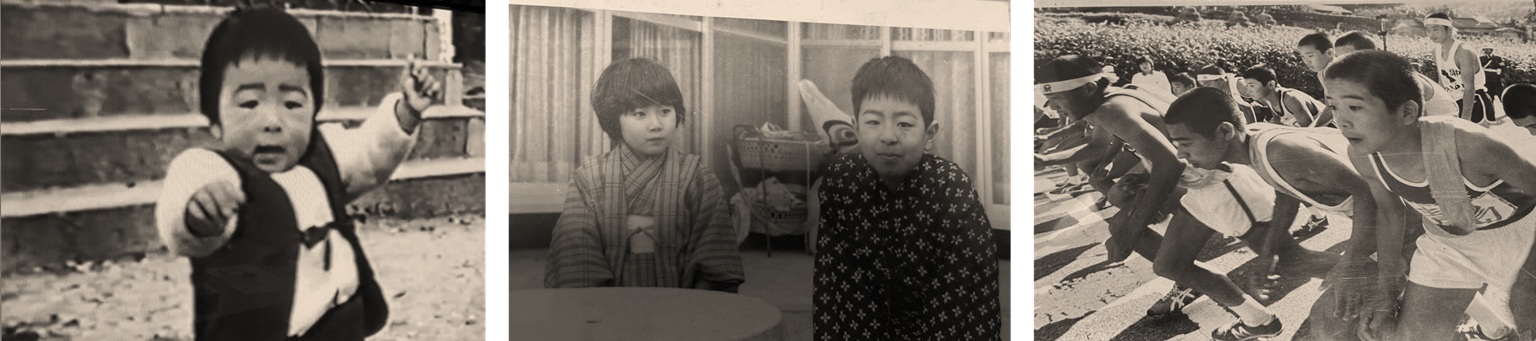
長崎県松浦市で生まれ、育った頃の思い出の写真(本人提供)
松井:そして日立入社後は、安全評価に携わってこられたわけですね。そうすると福島第一原子力発電所事故のときは最前線に立たれたのではないですか。
久持:現地ではありませんが、東京電力本店で事故対策にあたっていた政府と東京電力の統合対策本部に協力し、プラント状態の評価を実施していました。3月11日当日は、田町駅の近くにある原子力安全推進協会にいて、午後の会議を行っている最中に地震に遭いました。私はそのあとに海外出張の予定が入っていたため、電話もなかなかつながらない状態の中、とりあえず京成上野駅まで徒歩で移動して待機していました。夕方になってようやく会社からの電話が通じると、「東京電力様が大変だから協力してほしい」と。当日はすべて徒歩移動でしたし、会社のビルはエレベーターが止まっていて29階の緊急対策室まで歩いて上り下りしましたから、それだけでも大変だったことをよく憶えています。
松井:あの日、われわれ報道陣も東京電力本店に詰めていて、その場にいて、事態の深刻さが徐々に明らかになっていく様子をリアルタイムで体感しました。久持さんは最前線の情報に接していて、相当な危機感を肌で感じておられたのではないかと思いますが。
久持:さきほど、当時シビアアクシデント対策を行っていたと言いましたが、シビアアクシデントとは炉心に重大な損傷が発生するような事態で、まさにそのとき起きていたことです。炉心溶融の対応に関する手順書を東京電力様と一緒に作成したのも自分でしたから、当時も、状況に応じてすべきことはすべて頭に入っていて、説明することもできました。
ただ、現地からのすべての情報が把握できていなかったことは、もどかしかったですね。「もしわれわれが把握できていないデータが深刻な事態を示すものであったら」という不安と、「把握できるデータだけでやれることをやるしかない」、「まだ打つ手はある」という希望が交錯していました。心の底で、これが原子力事業に関わる最後の仕事になるかもしれないと覚悟しながらも、希望は捨てず、技術者として自分の持てるすべての知識を提供するという思いで対策にあたっていました。
松井:われわれも、ファクトを伝えたい、間違った報道は絶対してはならないというつもりでいましたが、データがきちんと公表されていても、機器の故障でデータ自体が正しくなかったということもありました。そのような覚悟を決めておられたというのは、久持さんにとっても厳しい状況だったのですね。当時はまだお若かったのでは。
久持:40代初めでした。
松井:その年代であのような重大な事故に冷静に対処されたというのは、相当の胆力をお持ちなのではないかと拝察します。そうした方が日立の原子力事業のトップに立っておられるということは、次に何か起きても、いや起きてはいけないのですが、心強く感じます。
では、その後もしばらくは事故対応に関わっておられたのでしょうか。
久持:そうですね、半年ぐらいは炉心の冷却に関する技術的サポートをしていました。それと平行して、現状の原子力プラントに適用可能な、事故の教訓を反映した安全対策についても東京電力様と一緒に検討を行いました。プラントの安全対策を担当してきた者として、できる限りのことをしたいという思いで取り組んでいました。

松井:当時すでにゼネラル・エレクトリック(GE)社(現 GEベルノバ社)との合弁会社であったわけですが、事故の対応でも支援などはあったのですか。
久持:米国側の姉妹会社、GE日立・ニュクリアエナジー(現 GEベルノバ日立ニュークリアエナジー)の安全対策技術の関係者とは連絡を取り合っていました。米国でもかつてスリーマイル島の原子力発電所事故でメルトダウンが起きています。それはGE社が設計した原子炉ではありませんでしたが、経験と教訓はエンジニアの間で共有されており、福島のシビアアクシデントについてもコントロールに関するアドバイスをもらっていました。
松井:日立GEニュークリア・エナジー社(現 日立GEベルノバニュークリアエナジー社)の設立が2007年ですから、もう少しで20年となりますね。協創関係も着実に深化してきたのではないかと思います。
久持:そうですね。もともと当社は日立とGE社がBWRの最新技術をグローバルに提供するために設立した会社です。GE社が2024年に原子力事業を含むエネルギー関連事業をGE Vernova(GEベルノバ)として分社化したことに伴い、当社も本年6月1日より商号を日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社に変更しました。米国の姉妹会社はGEベルノバ日立ニュークリアエナジーとなります。
GEベルノバ社はBWRを開発し、基本設計の改善に取り組んできた企業です。一方、日立製作所は1950年代から原子力事業を開始し、以来約70年にわたって原子炉の主要機器の製造と建設を継続してきました。両者が培ってきた技術と経験、得意分野を掛け合わせることにより、原子力技術の進歩と価値の向上に取り組んでいます。
協創の具体例としては、大型炉ではシンプルな設計で自然循環冷却が可能なESBWR(Economic Simplified Boiling Water Reactor)、英国での設計認証を受けた国際標準ABWRをさらに進化させた革新軽水炉HI-ABWR(Highly Innovative Advanced BWR)、小型炉では経済性と安全性を両立させた小型軽水炉BWR-300、革新的小型ナトリウム冷却高速炉PRISM(Power Reactor Innovative Small Module)などの開発や、既存原子炉のメンテナンスなどが挙げられます。原子力発電所の建設では許認可の手続きに時間と手間を要しますが、北米をはじめとする海外の規制に精通したGEベルノバ日立ニュークリアエナジーと、モノづくりや実証試験に強いわれわれが力を合わせることで、今後のグローバル展開を有利に進めることができると考えています。
(後編はこちら)

久持 康平
日立GEベルノバニュークリアエナジー株式会社 取締役社長
長崎県出身。1993年 九州大学大学院 工学部応用原子核工学 修士課程修了。同年 日立製作所入社。2017年 日立GE ニュークリア・エナジー株式会社(現 日立GEベルノバニュークリアエナジー)原子力エンジニアリング調達本部 原子力計画部長、2019年 原子力生産本部長、2020年 取締役(副社長)兼日立製作所 原子力ビジネスユニットChief Lumada Business Officer、2023年 株式会社日立プラントコンストラクション代表取締役 取締役社長。2025年4月より現職。

松井 康真 氏
フリーアナウンサー・ジャーナリスト
富山県南砺市(井波町)出身。富山県立高岡高校卒業。東京工業大学(現 東京科学大学)工学部化学工学科卒業。1986年 テレビ朝日にアナウンサーとして入社。「ミュージックステーション」でタモリさんと組んでMC、「ニュースステーション」ではスポーツキャスターを担当、「ステーションEYE」、「ワイドスクランブル」、「やじうまプラス」などで報道情報キャスターとして活躍。2008年 テレビ朝日アナウンサースクール「アスク」学校長。在職中の2年間の指導で全国に100人以上のアナウンサーが誕生。2011年3月の東日本大震災を契機にアナウンス部から報道局原発事故担当記者に異動。その後に宮内庁担当、気象災害担当、コメンテーターを歴任。2023年テレビ朝日退社後に個人事務所「OFFICE ユズキ」を設立。株式会社タミヤ模型史研究顧問、富山県南砺市アンバサダー、株式会社獺祭メディアアドバイザー。