統合システム運用管理 JP1 V8.5日立製作所 |
|
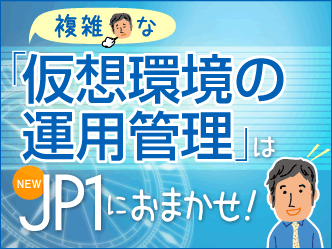 掲載日: 2008/10/27 |
|
|
◆変革の時代に、仮想化は効果的。だが新たな“課題”も…
【1】
企業に求められる課題とは
企業を取り巻く環境がますます多様化、加速化する今日。企業価値を高め、持続的な発展を遂げるためにも、「変化に即応できるITシステムの構築」は不可欠。一方、企業が直面する課題には「運用コスト削減」「サーバリソースの有効活用」「消費電力削減」などが挙げられる。
【2】
“仮想化”には追い風が吹いているか
これらの課題にとって、物理サーバ1台に複数の仮想的なマシン環境を構築する仮想化技術は効率的な解決策となりうるだろう。ハードウェアのコストも削減可能なことに加え、省電力・省スペース化にも有効な施策だ。しかし、“運用管理”という観点から見たときに、仮想環境には落とし穴ともいうべき、新たな課題が潜んでいる。
【3】
管理者に上乗せされる負荷
実際に仮想環境での運用を開始しても、当然ハードウェアの台数はゼロにはならず、物理サーバと仮想マシンは共存する。管理者には物理サーバに加え、“仮想環境の管理”という新たなタスクが生じることになるのだ。そして、運用管理が複雑化することは想像に難くない…。
【4】
仮想化で生じる“3つの課題”
まずは
障害監視
。障害の発生個所の迅速な把握とインパクト管理。2つめは
バックアップ
。通常業務に負荷をかけずにデータ保護を行う方策が必要となる。3つめは
リソースの最適化
。サーバの仮想化では、物理サーバのリソースを仮想マシンに効率的に割り当てることが不可欠となる。
――この3つの課題を解決するには、物理・仮想環境双方を一元監視し、可視化できるしくみ作りが必要だ。そのためにも有効なツールが日立のJP1。今回は、JP1が仮想環境の課題にどのように役立つかを紹介しよう。
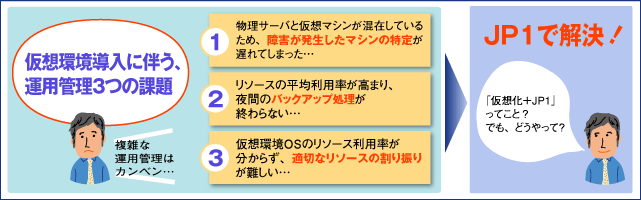 |
|
課題 1 |
「障害監視」を迅速に行いたい! |
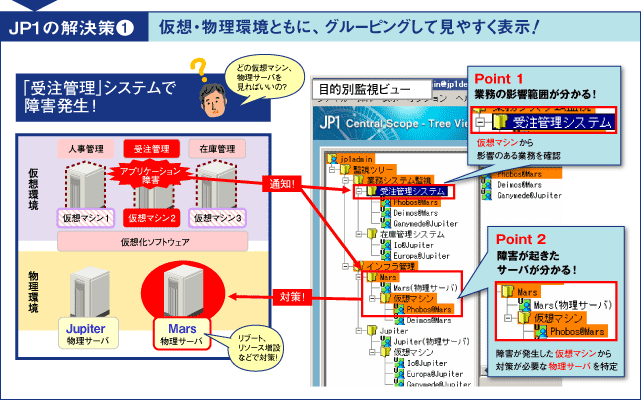
物理サーバ内に、複数の仮想マシンが共存する仮想環境では、障害が発生した場合には、それぞれ影響を及ぼし合う危険性がある。そのため、迅速に業務の影響範囲を特定し、障害が起きたサーバを特定しなければならない。
上図では、アプリケーション障害が起きた場合の例を紹介している。管理者に障害が通知されると、JP1の「目的別監視ビュー」にて、業務の影響範囲を確認
(Point1)
。「受注管理システム」に影響が出ていることが画面上ですぐに分かる。
同様に、障害発生サーバも特定できる
(Point2)
ので、対策も行いやすいというわけだ。
|
課題 2 |
「バックアップ」の効率を上げるには? |
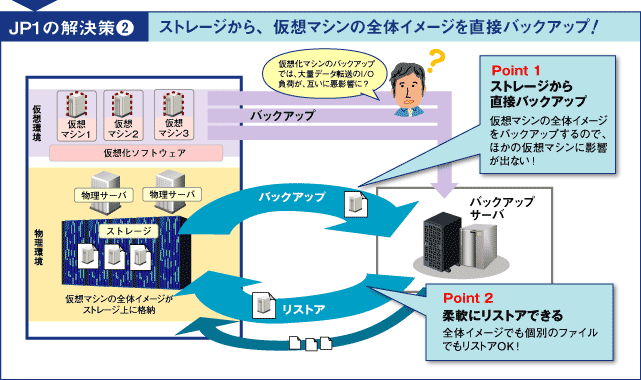
バックアップ処理は比較的リソースに余裕のある夜間などに行われるのが一般的。しかし、仮想化によってリソースの平均利用率が高くなると、夜間であってもリソースが不足し、バックアップが効率的に行えずにほかの業務に影響を及ぼす恐れがある。
また、1台の物理サーバが複数の仮想マシンのバックアップ処理を行うことで、I/O負荷が高くなり、リソース不足になる可能性も否定できない。
そこで、JP1はストレージから直接バックアップ処理を行うことでI/O負荷を最小限に行う。ストレージには、仮想マシンの全体イメージのファイルが格納されているので、その全体ファイルをそのままバックアップサーバに保存するというわけだ
(Point1)
。
また、仮想マシンの全体イメージでも、個別のファイルでも柔軟にリストアできる点も特長
(Point2)
。
|
課題 3 |
リソースの効率的な運用のために… |
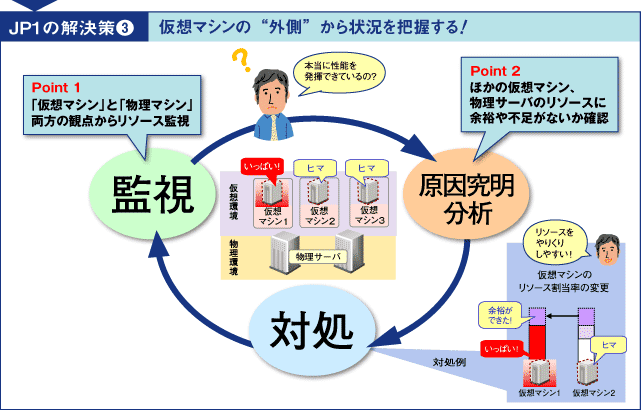
仮想環境では、「物理ハードウェア」と、「論理上の(仮想)ハードウェア」の2層あると考えられる。そのため、ゲストOS(仮想マシン上のOS)のタスクマネージャが「仮想ハードウェアのCPU利用率が100%」と判断した場合でも、物理ハードウェアにはまだ空きがあるという、“ねじれ”た状態が起こりうる。つまり、仮想環境では、リソースが適切に使われているのか分かりにくいわけだ。
この“ねじれ”を解消するのがJP1。「物理マシン」と「仮想マシン」のリソースを、仮想環境の外側から双方の観点で監視できる
(Point1)
。監視の結果、リソース不足が起きそうであれば、その原因を究明・分析して、ほかの仮想マシンに余裕がないかを情報収集
(Point2)
。
その結果、リソース不足が起きそうな仮想マシンに、余裕のあるマシンからリソースを割り振るなど適切な対処を事前に行うことが可能となる。
|
A社の場合 |
ハードウェア予算削減、消費電力削減のため、仮想化に着手 |
【Before】
■
仮想化で課題解決を試みるA社
製造業A社は、ビジネスにおける競争力を高めるためにも、業務効率化や様々なコストの見直しを図り、さらにはCO
2
排出量削減対策など社会的な取り組みを全社的に実施しようとしていた。もちろん、情報システム部門も例外ではなく、対策を検討・実施する必要に迫られていた。
情報システム部門は、まず、「サーバ台数削減など、ハードウェア予算と管理コスト削減」「消費電力の削減」と、課題を明確化。サーバ台数削減対策と省電力対策として、VMwareを用いた仮想環境を構築したが、物理サーバと仮想マシンの共存により、IT運用が複雑化し問題を抱えていた。
そこで、仮想環境の運用・管理にはJP1を導入。管理負担を抑えることで、さらなる効率化を目指した。
|
|
▲クリックで拡大 |
【After】
■
一元監視の視点を持った、仮想環境の実現
JP1を使って物理サーバと仮想マシンの稼働状況を一元監視することで、複雑化が心配されたA社の運用管理もスムーズに行われるようになった。また、仮想マシンの稼働情報が分かりやすい画面で表示されるので問題が把握しやすく、対処も容易に行える。
仮想マシンのCPU使用状態を「監視」する場合には、正常/警告/異常がそれぞれ赤・黄・青のランプで表示。直感的に状況を把握しやすい。CPU使用量に不足などが生じた際には、各種グラフで「原因究明・分析」ができるので、スムーズに適切な「対処」が行える。
こうして常に「監視⇒原因究明・分析⇒対処」の運用サイクルを実行することで仮想環境の運用最適化が実現。「ハードウェア予算と管理コスト削減」「消費電力の削減」といった課題の解消に成功したA社の情報システム部門であった。