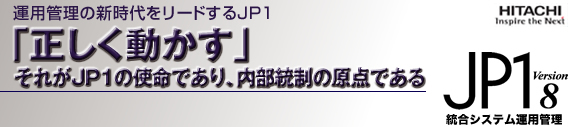|
――では、その内部統制と運用管理はどのように関係づけられるのでしょうか?
まず述べておかなければならないのは、当然のことながら運用管理ツールを導入したからといって内部統制すべてが実現する訳ではないということです。内部統制における運用管理は、システム全体の運用管理やセキュリティ管理、記録管理などの側面から、内部統制の強化を支援するものです。
JP1について言えば、ジョブ管理などによるシステム運用管理のほか、情報漏洩対策を中心としたクライアントPCの管理と統制などがそれにあたるでしょう。この2007年3月に発表した新バージョンJP1 V 8.1では、統制の対象をクライアントから、業務システムが動くサーバまで広げ、さらなるレベルアップを目指しています。
環境の変化に対応して、JP1も継続的なレベルアップを図っていこうとしています。
――システム運用管理に求められるものも、従来から変わってきているということでしょうか?
その通りです。企業内では新しいシステムがどんどん増え続け、システム運用管理の範囲が広がり負荷は高まる一方です。従来は、「増え続けるシステムを、いかに安いコストで問題なく動かすか」が運用管理者の仕事でした。しかし今では、そこで動いているのは何かと言えば、お客様に対するサービスであり業務です。システム運用管理の本質的な目的は、単にシステムを問題なく動かすことではなく、一歩高いビジネスレベルでのアウトプットの最大化を図ることへと移っているのです。これが昨年から提唱しているJP1 のテーマです。
私たちは、ツールを確実に動かすだけでなく、決められたプロセスを守り、人による判断も含めてPDCAをしっかり回すことで、ビジネスレベルのアウトプットを最大にしていくことを目指しています(図)。
ITを取りまく構造や法律が変わっていく状況下で、運用管理者も変わらないといけない時代になっています。TCO削減はもちろん重要なテーマですが、明らかにそれより一段高いレベルでシステム運用管理をとらえていかないといけない時代に入ってきたと感じています。コンプライアンスやJ-SOX法での動きは、まさにそうしたことの表れでしょう。
|