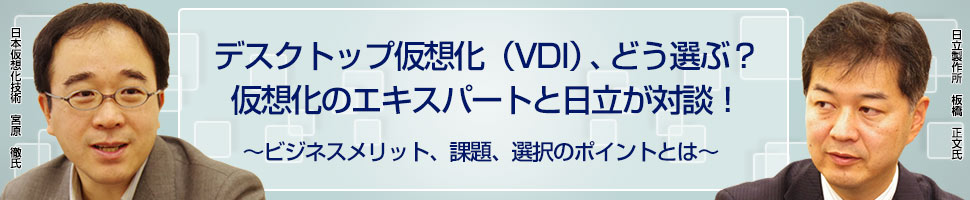
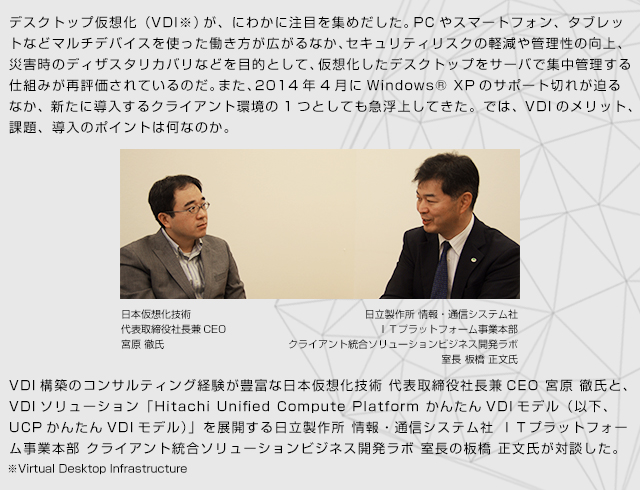
宮原氏: 最近のVDIを語るうえで欠かせないのがネットワーク速度の向上です。シンクライアントやリモートデスクトップといった仕組みは昔からありますが、通信速度が課題でした。今は、LTE* やWiMAXなどを使ってローカルPCと変わらない操作感が得られます。こうした環境整備が進んだという点は、これまでのシンクライアントなどとの大きな違いですね。
板橋: おっしゃるとおりです。たとえば、2004年頃ですと1Mbpsも出ないなかで顧客先でシンクライアントのデモを行っていました。どうしても描画が遅れるので、そのタイミングを見計らって、会話を挟んだりとプレゼンにも一工夫必要でした(笑)。
宮原氏: 今はパッと見ただけではローカルPCなのかシンクライアントなのかわからないほどですよね。メモリーやストレージも大容量化、高性能化が進みました。1台の物理サーバで200台程度の仮想マシンを稼働させても、それほどストレスを感じません。
板橋: そうですね。データセンター側で仮想化技術などがひろがったことで、ユーザーの要望にあわせた環境を提供できるようになった点は大きいと思います。そのユーザーとして国内最大規模の事例が、実は日立なんですよ。約10年前から自社ソリューションの導入をグループで進めていて、いま使っているのは8万人。今後も、グループ約33万人に対して適用範囲を拡大して行く計画です。
宮原氏: ベンダーであり、国内最大のユーザーであると。

宮原氏: VDIに対するニーズも変化しましたよね。かつてのシンクライアントはどちらかというと、セキュリティを確保したい、社内オペレーションを簡素化したいといった"守り"の観点に立ったものでした。ところが今は、営業に機動力を持たせたい、ワークスタイルを変革したいといった"攻め"のニーズが多いと感じます。具体的には「タブレットからPCのアプリケーションを使いたいがどうすればいいか」「VDIを使ってBYOD* の仕組みが実現できないか」といった相談です。そのあたりはどうでしょうか。
板橋: スマートフォンやタブレットの利用が広がったことで、それらを経営の武器にしようという動きは進んでいると思います。タブレットから売上レポートなどをすぐに確認できるとかなり便利になります。また、業務の用途によって使うデバイスを選択して利用しています。編集作業はPCで、簡単な確認作業はタブレットでと使い分けることで、より効率的な業務が可能です。もろちん、ローカルPCにデータを保存しないようにすることで、情報漏えいのリスクを減らしたいといったニーズも変わらず存在します。
宮原氏: なるほど。昨今はWindows® XPのサポート終了も大きなトピックになっていますよね。VDI上で一部アプリケーションを延命できるのではないかとの期待もありますが、いかがでしょう。
板橋: 確かに、そのようなニーズはよく聞きます。Internet Explorer® 6向けに作成された業務アプリケーション群をどうするか調べたところ、検証と手直しで数億円かかる!などといったケースは少なくありません。そうした環境向けに、必要なモジュールの動作だけを許可することで、セキュリティーリスクを最小化しつつWindows® XP向け業務アプリケーションを延命できるようにするソリューションも開発しています。
宮原氏: 日立さんの自社導入は、そもそもどういう経緯だったのでしょうか。

板橋: きっかけは情報漏えいの防止でした。弊社の事業は多岐にわたりますが、それぞれの社員が顧客企業の機微な情報を扱っています。当時は、ノートPCにデータを入れて持ち歩いていたのですが、万一それらを紛失するとたいへんなことになる。そこで「事故は起きるかもしれない」から「事故は必ず起こる」という発想で、2004年から経営トップ主導で業務情報を保持しない「シンクライアント」と、業務アプリケーションを安全に利用する「セキュアクライアントソリューション」を社内用に開発するプロジェクトを発足しました。
また、2006年頃からは「ワークスタイル変革」をテーマに、営業を中心にさらにユーザーを拡大し、座席のフリーアドレス化やWi-Fi導入などと並行して、どこにいても仕事ができるような取り組みを進めていきました。
宮原氏: 利用シーンは?
板橋: 社員それぞれの業務内容にあわせ、適切な環境が支給されています。私は、「シンクライアント」とタブレットを利用しています。ネットワークにつながる環境があれば「いつでも」「どこでも」自分のデスクトップ環境を利用することができます。海外出張など長期間オフィスに戻らない時期でも、承認作業などを停滞させることなく業務を推進できる点はとても便利ですね。

宮原氏: 最近では、事業継続性やディザスタリカバリに対するニーズも増えていますね。 データを地震などに強いデータセンターに置かれたサーバで集中管理するので、VDIは災害対策にもなります。3.11(東日本大震災)の時、実際の効果はどうでしたか?
板橋: 自社でVDIを日常的に利用していたことは、確かに功を奏しました。震災発生の際、シンクライアント端末を使っていた人は、迅速に取引先に問い合わせを行ったり、緊急連絡を行ったりと、全国各拠点で事業を継続することができました。まさに身を持って効果を実感したわけです。最近では台風で交通が大きく乱れた際も、足止めされた駅近くのコーヒーショップでいくつかの決裁とWeb会議での資料レビューを行いました。
宮原氏: これほど大規模な運用ですと、得られるノウハウや経験も貴重ですね。サーバなどはどういった構成になっているのですか。
板橋: 国内については、複数のデータセンターで一定の人数ごとに分けて管理しています。どのような仕組みにすれば安定するか、パフォーマンスがでるかといったノウハウは、日々蓄積している状況です。社外からはインターネットからVPN* 接続します。ゲートウェイのサーバで負荷分散しています。
宮原氏: ちなみに物理サーバ1台に収容しているのはどのくらいですか。
板橋: 多人数を1台に収納する仮想デスクトップの安定運用は業務に直結しますので、当社の場合は安定性や可用性を考慮して、物理サーバ1台につき仮想マシンは50台程度の構成を推奨しています。(BladeSymphony BS500の場合)
宮原氏: 一方で、VDIに対しては過度な期待や、実際に導入してみないとわからない課題もあると思います。たとえば、コストの見積もりです。新たに機器が必要になるケースが多いので一見高くなるのですが、集中管理によって運用コストは下がりますよね。そういった目に見えないコストの見積もりが難しく、経営サイドに納得してもらう際に苦労すると思います。
板橋: そのとおりだと思います。サーバ仮想化と同じようにコスト削減の手段と考えてしまうと、導入の障壁は高くなってしまいます。逆に、なんでもやろうとして、意に沿わない結果になってしまうこともあります。
宮原氏: VDIを導入目的にしないということですね。
板橋: そうです。技術選定から入るのではなく、まず、利用する人、利用するイメージを明確にして、それにあったソリューションを探すことが大切だと思います。弊社では、それを支援するための個別ワークショップを開設しています。
宮原氏: 個別ワークショップというのは。

板橋: VDI導入に際し、どのようなステップを踏めばいいのかをご提示、業務利用の姿をお客さまと一緒に描くとともに、これまでの構築・運用で培った経験知を生かしてお客さまの予算・目的に合わせて適切なソリューションのご案内をするものです。お客さまによっては、VDIといっても「業務での使い勝手が分からない」「投資対効果がみえない」「既存業務への影響はどうか?」「どの実装方式を選定すべきか」と検討すべき項目が多岐にわたり悩んでしまうケースも見受けられます。ワークショップを通じて、利用・運用のイメージをお伝えし、お客さまと二人三脚でプロジェクトを推進したいと考えています。
宮原氏: そういったあたりで、8万ユーザーのサポート経験が生きてくるのですね。
板橋: そうですね。運用面での意外な落とし穴や対応策についても社内での運用ノウハウが蓄積されているほか、国内の「クライアント仮想化ソリューション市場」トップシェアの実績※が示すとおり幅広いユーザーへの導入実績がありますので、構築から運用まで幅広くサポートできると思います。
板橋: 名前のとおり、VDIをかんたんに導入できるようにしたものです。ポイントは2つあります。1つは、運用開始までの期間・工数を短縮したことです。構築ノウハウや推奨ハードウェア・ソフトウェアをパターン化し、工場でプリセットして提供します。従来は検討期間を含め5ヵ月かかっていたところを2ヵ月程度に短縮しています。
宮原氏: もう1つのポイントというのは。
板橋: かんたんな運用管理ですね。仮想化環境をかんたんに管理できる運用管理ソフトを標準で添付し、運用支援ドキュメントや操作トレーニングも提供します。それから、稼働後の基盤に対するお困りごとのワンストップサポートを提供します。

宮原氏: たしかにVDIというと、いろいろな組み合わせがあって、導入も難しいですよね。メニューを見ると構成が3つあるようですが、基本的にはこのどれかを導入することになるのですか。
板橋: トライアル構成、スタンダード構成、エンタープライズ構成の3つです。ユーザー数が10ユーザー程度ならVDIの使い勝手を手軽に簡単にご確認いただけるトライアル構成、25〜1250ユーザーであれば信頼性とコストのバランスを考慮したVDI本番環境の標準構成スタンダード構成、全社展開など大規模利用を見据えるならエンタープライズ構成としています。
板橋: ただ、これは固定的なプランではなく、企業のシステムの状況に応じて変更することもできます。VDIはビジネスを成長させるためのITインフラでしかありません。手間をかけずに使っていただき、最終的には、VDIの上でどのアプリケーションをどう動かしていくかが大切なのです。
(1)利用イメージを明確にしてから、技術、ソリューションを選ぶこと
(2)スモールスタートで課題を洗い出し、徐々に利用者を増やしていくこと
(3)VDIの導入目的をビジネスの機動力とする"攻め"に変化させていくこと
宮原氏: むしろ、かんたん導入することによって、VDIがビジネスにどんな価値をもたらすかをより深く検討できるのかもしれませんね。

板橋: そのとおりだと思います。PoC* のような検証サービスも行っていますので、そこでシステムの課題やビジネスへの貢献度を検証していくことができると思います。
宮原氏: さて、今後の展開はどうでしょうか。
板橋: VDIは、アプリケーションやデータへの自在なアクセス手段を確保するためのソリューションだと考えています。端末からサーバまでをどうつなぐかということですね。その意味では、次のステージで課題になるのは、どうコミュニケーションの向上を図るか、業務効率を向上させるかといったコンテンツに関するソリューションをお客様にご案内していければいいと思っています。
VDIで仮想環境を有効に利用するなら、Windows® Server 2012 Datacenterがオススメ
1台の物理サーバで必要な数だけWindows Server®の仮想インスタンスを実行したい場合は、Windows Server® 2012 Datacenterなら無制限に実行できます。
日立製作所がハードウェアと合わせてOEMライセンスを提供することで、お客さまは手配しやすくなり、Windows Server® 2012をインストールする手間を簡略化でき、購入後すぐに利用できます。