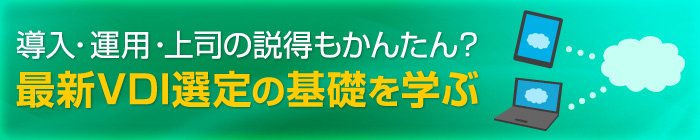
![]()
昨今、場所や時間を問わずに、ITを使って効率的に働く方法が話題になっています。その背景にはインターネット回線の高速化やアプリケーションのWeb化などが挙げられます。事実、多くの企業が恩恵を受けると思われる、その理想的な“仕事術”とはどのようなものでしょうか?
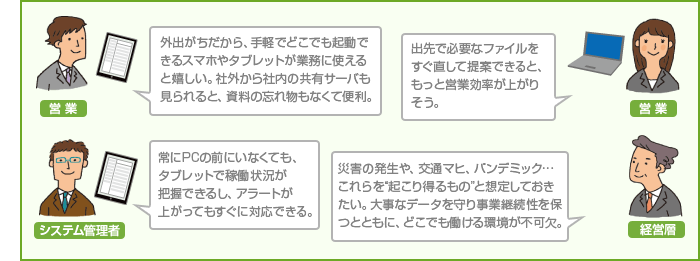
それぞれの立場から、理想的な“仕事術”を語ってもらいましたが、まとめると次のようになります。
●社外で仕事しやすい環境…外出の多い営業、在宅勤務者など多様な働き方に対応
●災害時、交通マヒ…データを守るとともに事業継続性を担保、場所を問わない勤務環境
●アプリケーションのWeb化…データに安全にアクセスできるようなシステム
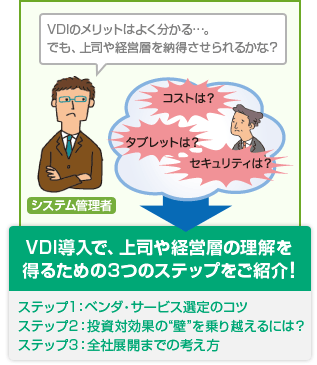
ただし、それにはもちろん、課題も残されています。
例えば下記のように。
●紛失・盗難による情報漏洩
●Webアプリケーションの、最新ブラウザへの対応
セキュリティ対策はもはや改めて指摘するまでもないかもしれません。特にWebアプリケーションのライフサイクルについては、昨今のWindows® のマイグレーションでその大変さを痛感している方も多いのではないでしょうか。
このような中、注目を集めているのが「デスクトップ仮想化(VDI)技術」です。その技術をクライアントコンピューティング環境の中核に導入することで“理想の仕事術”につなげられると期待を集めています。しかし、導入までは「コスト」や「上司を説得できる稟議書作成」、「経営陣の説得」…などが悩みどころ。そこで今回は、VDIを本気で導入したい方にお教えしたい、3つのステップをご紹介します!

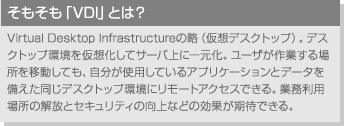
情シスはVDI導入を考える時に、何をすべきか…。
製品選定から稟議書作成まで、多様なプロセスがありますが、「3つのステップ」として、その課題や導入にあたり検討すべきことなどを整理しました。
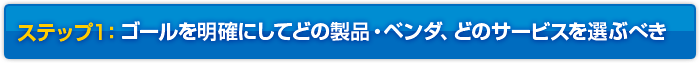
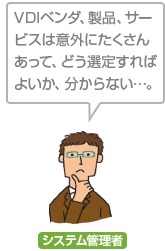
一口にVDIといっても、さまざまなベンダが多くの製品・サービスを提供しています。そのため、それぞれを比較し、自社に最適なものを選ぶというのは、意外にハードルが高いかもしれません。技術的な部分やスペック情報で比較しても違いがよく分かりませんし、何を決め手にしていいのか分からない…という状況になりがちです。
そこでまず、ベンダ/製品・サービス選定のためには、VDIを適用するゴールとなる業務範囲や目的を明確にすることが重要です。例えば、「情報漏洩防止を狙い全社一斉展開なのか」「外回り・出張の多い社員を対象とした業務改革なのか」などです。こうした観点を持つことで、どのくらいの規模感(コスト)で、どこから始めるべきなのかが見えてくるでしょう。また、自社に適したソリューションを提供してくれるベンダ/製品・サービスを絞り込んでいくこともできるでしょう。
更に、VDIを実際に導入している企業の事例を研究したりワークショップに参加するのも有効です。ベンダにさまざまな質問を遠慮なくぶつけて、自社の最適解を見極めましょう。
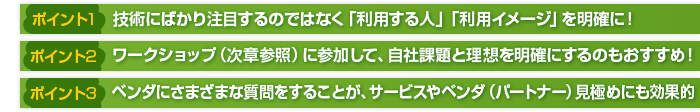
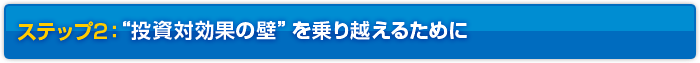
ここでは、VDIで得られるメリットと、それに対するコストの考え方について整理します。まずは、VDI導入で得られる5つのメリットをご紹介します。
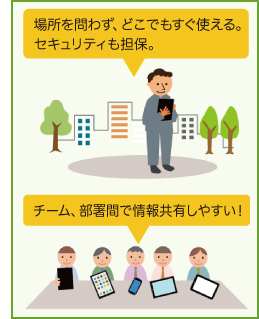
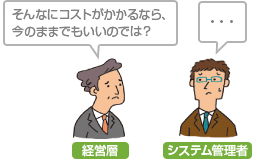
――このようにメリットが大きいVDIですが、導入で最大の壁となるのが、そのコストかもしれません。推進Go/No GOを決定する経営陣に対し、どのような稟議を通せばよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
このような悩みに対し、有効な4つのポイントをご紹介します。
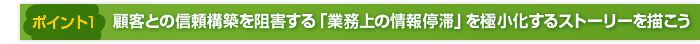
社内の資料にアクセスできるのは「自社デスク上のPC」のみという環境では顧客先での提案、回答などに時間がかかりがち。しかし、VDIならば顧客の要望にあった資料を提案活動の場で提示し、その場でプランをカスタマイズするなど、これまでの概念よりもスピーディーな働き方が可能となるのです。

「承認担当者が海外出張で稟議が1週間停滞」「上長の確認を得ないと作業を進められない」…このような場合でも、VDIならばオフィス在席にしばられないので、すばやく承認・回答が可能に。よりいっそう経営スピードを促進することが可能になるでしょう。

経営陣の理解を得るためにもおすすめしたいのが、実際にVDIの魅力を体感してもらうこと。例えば業務内容に合わせてPC、タブレット、スマートフォンなど多様なデバイスを使い分けることで得られるメリットを実感してもらうのです。デバイスごとに得意な業務がありますので、VDI活用で新たに得られるビジネスメリットや使い勝手の限界などを具体的に理解してもらえるはずです。
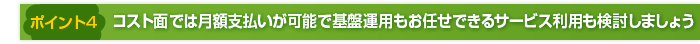
稟議書にコストを記載する際には、企業のIT投資額に見合った見せ方をすることも重要。いきなりこれまで以上のコストを記載するのは得策ではありません。特に、初期コストに課題を感じている企業も多いと思われます。例えば昨今、必要な機材は自社スペースに設置して、費用や運用を月額で支払うことのできるサービス(DaaS型サービス)も登場しています。自社のIT投資額に見合ったサービス提供形態を選択すること、それも重要なポイントといえます。
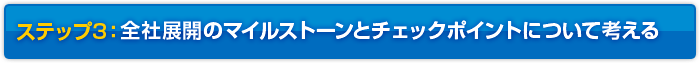
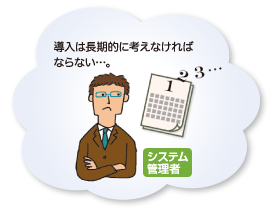
「さあ、VDIの稟議も無事通り、早速、企業システムにVDIを導入しよう!」となった場合に考えなければならないのが、全社展開のマイルストーンとチェックポイント。なぜなら、VDI導入は比較的長期にわたることが予測されます。途中、状況に変化が応じた場合でも、柔軟に対応できるような備えが必要となるからです。
また、VDIを全社展開すれば、すべての業務システムがVDI上で動くことになりますので、システムが停止した場合の業務への影響は多大なものとなります。導入にあたって押さえるべきポイントは3つです。
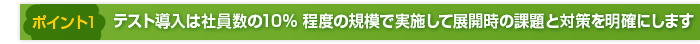
まず、テスト導入をすすめる必要がありますが、社員数の10%程度の規模で実施することがおすすめです。大きな課題が発生しても方向修正が可能なレベルだからです。
VDI導入にあたっては、2〜3ヵ月のテスト導入を行い、その際に発生した課題を整理しながら、できる技術の組み合わせで、全面展開に向けて最適な方法を明確にしていくことが求められます。

VDIといっても、その実現方法には複数の方式や複数のデバイスが存在します。また、業務パターンによって、「モバイル性」「アプリケーションデータとのつなぎ方」も異なります。業務内容(要件)と方式の特長を理解した上で、最適な方式を選択。適切な「コスト」と「アプリケーション実行の自由度・独立性」を選択しながら、業務パターンごとに社員をブロック分けして拡張していきましょう。

全社展開に向けブロックごとにテストを実施しながら導入を進めると長期プロジェクトとなるケースがあります。そうした場合、新しいデバイスが発売されたりと、プロジェクト途中で最適な技術が変更になる可能性が出てきます。また、VDIの活用が定着していくと、「マルチデバイスで使いたい」「個人で所有するデバイスを業務で使いたい(BYOD*)」といった要求も増えてくるでしょう。このような要求に対し、利便性や機動性の向上、企業としてのIT統制バランスなどを検討しながら、ビジネス利用の最適解に向けて段階的に拡張や調達ができる技術を選択することが重要といえるでしょう。
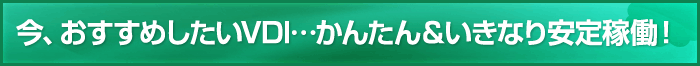
前章で解説してきたVDI導入のステップですが、導入・運用にあたっては、検討しなければならない項目が非常に多く、また関連性も難解です。
そこでVDI提供ベンダであり自らもユーザとして業務活用している日立製作所(以下、日立)に相談した場合、どのようなメリットがあるかについてご紹介します。
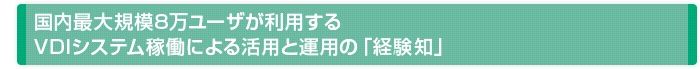
「なぜ日立のVDIか?」というと、日立は2004年から全社的にVDIを導入。既に9年もの導入・拡張・運用を行っている経験を持ち、今や日立グループ全体で国内最大規模の8万人が利用するVDI環境を運用しています。大規模環境のみならず、100名単位の規模の部署やグループ企業でも導入しているという柔軟性があります。このシステムの構築・運用の際に蓄積した経験知を活かし、ユーザに対し、VDI導入に向けた検討〜導入後の運用まで幅広くサポートすることが可能です。
このような実績が評価され、国内の「クライアント仮想化ソリューション市場」でも1位となっています*。パートナーとして日立を選定する際の大きなポイントになるのではないでしょうか。
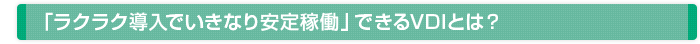
VDI構築にあたっては、「十分なネットワーク帯域の確保」「多数の仮想マシンが稼働するためシステムを安定稼働させるための仮想化技術の最適化」など、高度な技術を複数組み合わせて導入する企業に最適なシステムを組み上げる必要があります。
このように、技術ハードルも高いことから、その導入・運用にあたっては、不安も多いところ。そこで日立は、豊富な実績にもとづくシステム設計、構築のノウハウを活用し、VDIの共通的な要件に適合するよう最適に設計された垂直統合型製品「Hitachi Unified Compute Platform かんたんVDIモデル(以下、UCPかんたんVDIモデル)」を提供。VDI環境の試験導入、小規模から大規模まで幅広いお客様のニーズに対応します。
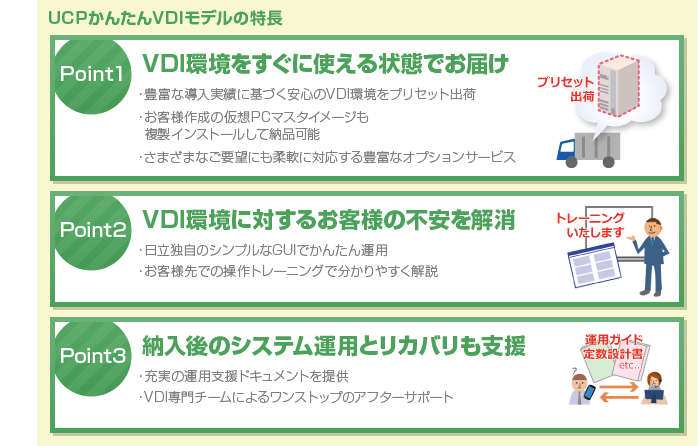
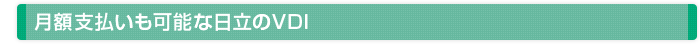
日立では、お客様のニーズにあったクライアント基盤を選択いただくため、必要なサーバなどを一括購入して運用するパターンのほかに、お客様先センタに機器を設置し月額払いで運用するサービスや日立データセンタを利用するパブリッククラウド型のサービスなど複数のサービスを提供しています。
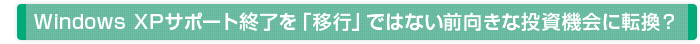
2014年4月に迫るWindows® XPサポート終了。しかし、新しいOSへの移行が難しいソフトウェア資産を持つ企業も多いのではないでしょうか。
そこで日立では、あらかじめ登録されたソフトウェアのみ動作を許可するホワイトリスト方式のセキュリティソフトを導入するホワイトリスト型のオプションサービスも提供。サポート終了のタイミングではなく、業務のライフサイクルの観点から業務インフラの段階的な改善を行うことが可能となります。
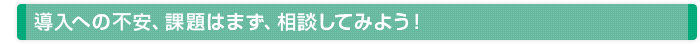
VDIを社内にどのような順序で導入すべきか?本当に自社で運用できるのだろうか…など、さまざまな不安を感じたらまずは、日立に個別ワークショップの依頼をしてみてはいかがでしょうか。これまでの実績にもとづいた、自社に適したVDI環境を作るためのアドバイスが得られることでしょう。“技術ハードルが高い”ことで感じる不安も解消されることでしょう。
また、導入以降も、運用面でもサポートが充実している点も日立の魅力です。小さく導入して拡張したい、運用中の基盤監視、操作運用をサポートしてほしい…といったことまで、多くのことに対応可能です。是非この機会に、日立に相談してみてはいかがでしょうか?
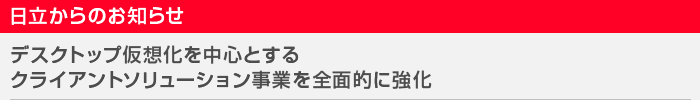
2013年12月11日、新たなビジネス価値の創出に最適なクライアント環境を実現する製品・サービスを体系化した日立クライアント統合ソリューション「Hitachi unified client experience platform」の発表が行われました。
日立グループが提供する高信頼なクラウド、セキュリティ、ビッグデータ利活用など幅広い技術・製品・サービスを基盤として、多様なVDIソフトウェアや最先端のスマートデバイス、コミュニケーションツール、パブリッククラウドサービスなどを組み合わせて、企業の社内外のデータや経験・知識の統合的な活用による新たなビジネス価値の創出に最適なクライアント環境を実現します。
日立グループのVDIをはじめとするクライアント環境に関する専門的な経験・知識を有する「クライアント統合ソリューションビジネス開発ラボ」が中心となり、お客さまのイノベーションの創出を支援していきます。
関連リンク